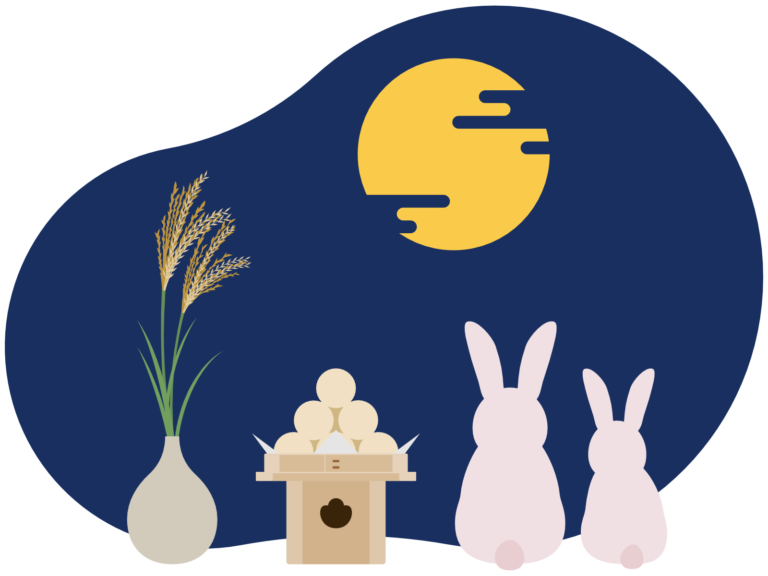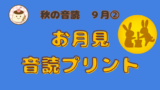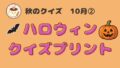2025年の十五夜は10月6日!お月見の話題で、リハビリや脳トレをしよう!
2025年の十五夜は10/6(月)です!
この記事では以下の情報をお届けします。上にある目次をクリックして必要なところからご覧ください。
・お月見に関する雑学・豆知識
・お月見の雑学を、認知機能や言語機能のリハビリに活用する方法・アイディア
お月見に関する雑学・豆知識
お月見の起源と始まり
日本で初めてお月見を楽しんだのは平安貴族たち?
- お月見の風習が日本に伝わったのは、奈良時代~平安時代ごろ、中国からです。
- 平安貴族たちが、中秋(旧暦8月15日)の夜に「観月の宴」を楽しんでいたのが、日本での「お月見」の始まりと言われています。
- 「観月の宴」では何をしていたのでしょうか?
- 池に浮かべた船の上から、水面に映った月を見たり(舟遊び)
- 杯に月を映してお酒を飲んだり
- 和歌を詠んだり
- 管楽の演奏を聴いたり
などして楽しんでいたようです。雅ですね!
徐々に庶民へと広がり現代の形へと近づいて・・・
- このような貴族の風習が、徐々に庶民にまで広がっていきました。
- 農民たちにはもともと「月」への信仰心が強くありました。
- お月見は、農民たちの間で、「月」を神様とあがめ、秋の実りを感謝したり豊作を祈願する行事へと変化していきました。→これが、お供え物の始まりと言われています。
- 農民にとって、月の満ち欠けは農作業の時期を知るために大切なものでした。
- 月の神様である「月読命」は、農耕の神様でもあったという説があります。
現代における「お月見」
- 現代でも、各地でお月見イベントが開催され、親しまれています。
- また、この時期になると、卵の黄身を月に見立てて「月見○○」などの期間限定グルメもたくさん発売されます!
- 月見バーガーや、月見牛丼、月見そば、月見うどん などがありますね。
- うさぎのモチーフや、月の形をイメージしたお菓子もたくさんあります。
- 家のベランダや縁側から大きな満月を眺めるだけでも神秘的な気持ちになるという方も多いのではないでしょうか。
十五夜の日は、現在の太陽暦にあてはめると毎年日付が変わります。
2025年の十五夜は、10月6日(月)になります。
お月見は十五夜だけじゃない!?
- お月見は十五夜だけではありません。
- 旧暦9月13日の「十三夜(栗名月・後の月)」も古くから大切にされてきました。
- 旧暦8月15日の「十五夜(中秋の名月)」は中国由来ですが、「十三夜」は日本生まれの風習です。
- 平安時代に宇多天皇が始めたと言われています。
十五夜と同様に、現在の太陽暦にあてはめると毎年日付が変わります。
2025年の十三夜は、11月2日(日)になります。
十五夜の別名は「芋名月(いもめいげつ)」。十三夜は?
- 十五夜は「芋名月」と呼ばれ、里芋など秋の収穫物を供えます。
※「芋名月」の「芋」は、薩摩芋ではなく、「里芋」だそうです。 - 十三夜は「栗名月・豆名月」とも呼ばれ、栗や枝豆を供える地域もあります。
両方見ないと縁起が悪い?
- 昔は、十五夜と十三夜の両方を愛でるのが粋とされていました。
- また、十五夜の月だけを見て十三夜の月を見逃すのは縁起が悪いと考えられており、「片見月」と言われていました。
- 平安貴族の間で、船から水面に映った月を眺める「舟遊び」がありましたが、これは、中秋(十五夜)に空と水面の両方の月を見ることで2つの月を見たことになり、後の月(十三夜)の月を見なくてもよいという意味もあったようです。
「中秋の名月」は必ずしも満月とは限らない
- 十五夜は、旧暦の8月15日の夜を指します。
- 月の満ち欠けの周期の関係で満月に近いことが多いですが、必ずしも満月とは限りません。
お供え物:お月見団子とススキ
- お月見団子は、一般的には、満月に見立てた丸い形が特徴です。
- しかし、地域によって形や数、供え方が異なります。
- 関西では俵型のお団子に餡子をかけたものをお供えする地域もあります。


- ススキは、葉や切り口が鋭く、魔除けの効果があると信じられていました。
- また、収穫前の稲穂に似ていることから豊作を祈願する意味も込められています。
- 月の神さまが宿る「依り代(よりしろ)」の意味合いもあります。
(※依り代は、神様が一時的に宿るものという意味)
月でウサギが餅つきをしている?
- 地球から見える月の表面には模様が見えます。
- この模様が、日本では「ウサギが餅をついている姿」に見えるとされてきました。皆さんにもそのように見えますか?
- これは、インドのお話がもとになっているとも言われます。
- アジア各地でも月の模様を動物にたとえる習慣があり、中国ではウサギが不老不死の薬を作っているといわれるなど、似た伝説がいくつか存在します。

※この話題は、All Aboutの記事が面白かったです。ほかの国では何に見えるのか、などまとめられています。
「お月見」の話題で脳トレ!
お月見に関する文章を音読する
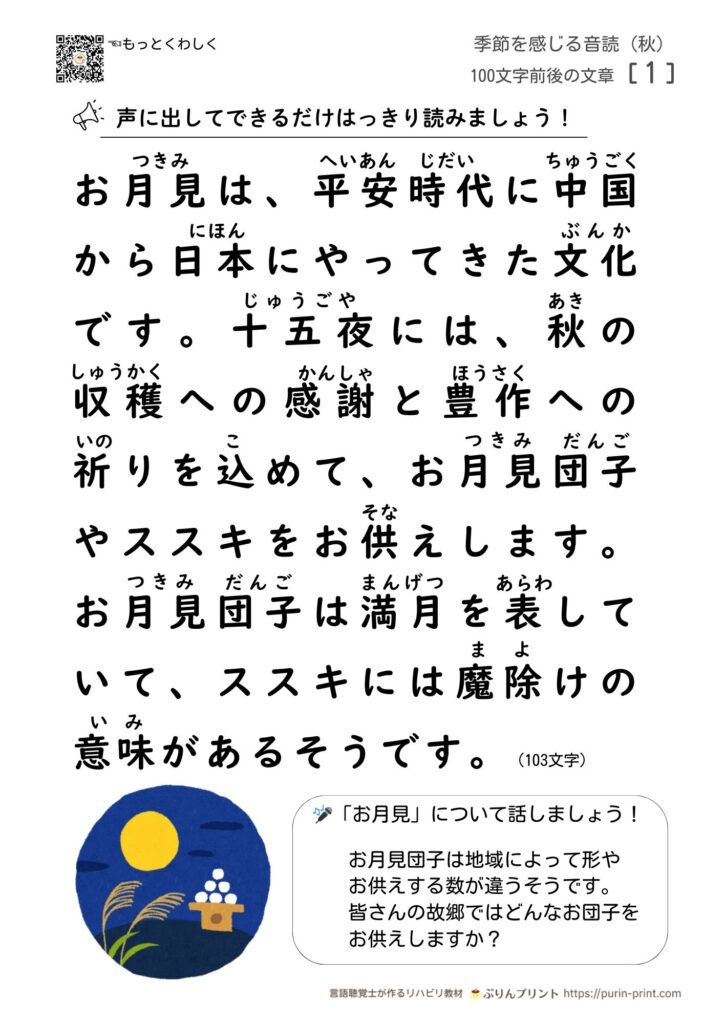
ぷりんプリントでは、お月見の雑学・豆知識を、100字位の文章にまとめたオリジナルのプリントをご用意しています。
ダウンロードは下記のリンクからどうぞ。
「ルビ有り」がおすすめです。
💡音読プリントの活用方法
・プリントの文章を声に出して音読する。
・プリントの内容についてお話する。(内容に関する質問に答えてもらう)
・お月見に関して他に知っていることを話していただく。
・お月見に関する思い出を話していただく。
お月見の写真やイラストを見てお月見の思い出をお話しする(回想法)
回想法での質問の例
- お月見したことがありますか?
- 子供のころはお月見をしましたか?
- お月見団子は手作りでしたか?どんな形でしたか?
- 地域ならではのお月見の風習はありましたか?
- お月見の時に食べるものってありますか?
- 「月見」が名前つく食べ物を何か知っていますか?
(月見そば、月見うどん、月見バーガー・・・) - 月に関する歌やお話はどんなものをご存じですか?
(「♪十五夜お月さん」「♪月」「♪うさぎうさぎ」「📖かぐや姫」等)
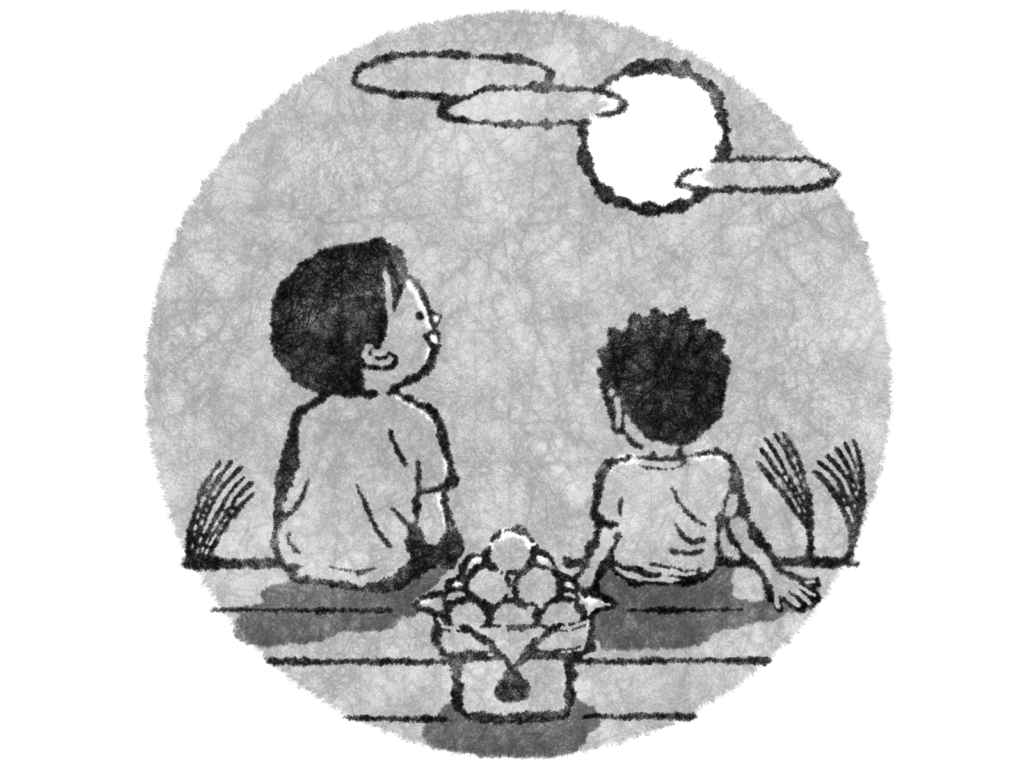
月に関する歌を歌う
歌詞カードは大きく見やすい文字で作りました。
一緒に歌った後はぜひ、お月見の思い出をお話してみてください♪
💡歌の活用方法・アイディア
- 歌詞の一部を隠して、歌詞の穴埋めクイズにする
- 歌詞を書き写してみる
- 歌わずに、声に出して読んでみる
- 身振り手振りを付けて歌ってみる
- デイなどでは、特定の歌詞の部分で、決まった身振りをするなどのルールを決めて、みんなで挑戦するのも楽しいです。
- 例えば
- 「ウサギ」→手を頭の上にあげてウサギの耳のジェスチャーをする
- 「跳ねる」→座ったまま足を上げて跳ねる動きをする
- 「丸い」→両手を挙げて大きな丸を作る
♪うさぎうさぎ (うさぎ うさぎ 何見て 跳ねる 十五夜お月さん 見て 跳ねる)
♪月(でた でた 月が まるい まるい まんまるい 盆のような月が)
月に関する言葉を思い出す(語想起(語列挙)課題)
語想起(語列挙)課題のテーマとして、「月」や「お月見」を指定して言葉を思い出します。
💡語想起(語列挙)課題とは?
あるテーマに沿って思い出せる単語を次々に出していく課題です。
この課題は、たくさんの意図がありますが、代表的なのは以下のポイントです
- 思い出したい言葉を「頭の中から探し出す力」を鍛える
- 似たもの同士を頭でグループ分けする力(カテゴリー化)を鍛える
- 過去の経験や知識を呼び起こす力を鍛える
声掛けの仕方の例:
「【月】と聞いて、思い出す言葉をたくさん挙げてみましょう!」
「【お月見】と言えば、どんな言葉が思い出されますか?一緒に考えてみましょう!」
💡言葉がなかなか浮かばない時は、こんな風に考えてみましょう。
(支援者の方はヒントとしてこのようにお声掛けしてみましょう。)
・月の形を表す言葉はどんなものがありますか?
満月・三日月・半月・新月・上弦の月・下弦の月 など
・お月見でお供えするものを思い出してみましょう
お団子、ススキ、サツマイモ、サトイモ、栗など
・月の中にいると言われている動物はなんでしたっけ?
日本では、「ウサギ」が餅つきをしていると言われることが多いですね。
アジア圏以外では、カニやワニなどほかの動物が見えるという言い伝えも多いです。
科学や宇宙の話題が好きな方にはこんな質問もいかがでしょう!?
・月に初めて着陸した宇宙飛行士はご存じですか?「アーム○○○○○船長」です。
アームストロング船長
※「これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍である」(That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.)という名言を残しました。
・月に初めて到達した宇宙船の名前をご存じですか?
最初に「ア」がつきますよ、「ア〇〇11号」です。
アポロ11号
こちら↓で、アポロ11号が月面に到着した時のニュース映像を見られます。
▶NHKアーカイブス アポロ11号 月面着陸(1969年7月20日)
想起する言葉の例
満月、まんまる、丸い、半月、三日月、お月見、ススキ、ウサギ、ウサギの餅つき、クレーター、アポロ11号、アームストロング船長、皆既月食、吸血鬼、スッポン などなど・・・
十五夜、十三夜、中秋の名月、お団子、ススキ、里芋、夜、9月、10月、月見そば、月見バーガー、などなど・・・
脳トレに!お月見の音読プリントや月にまつわる歌の歌詞カードのリンク


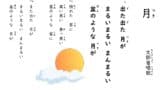
応援メッセージだけでも大歓迎です!匿名・公開の選択も可能です。
ご支援は100円から。クリックしてもすぐにお支払いにはなりません。
いただいた応援は、教材づくりの励みになります。